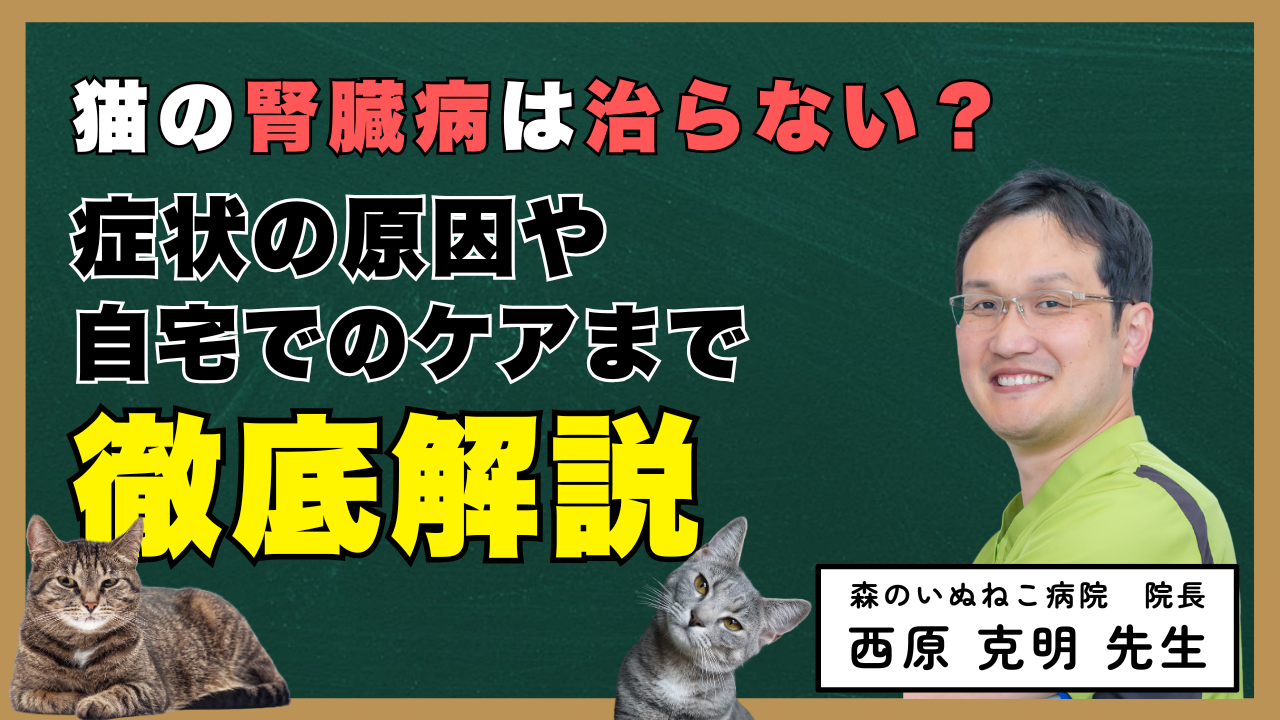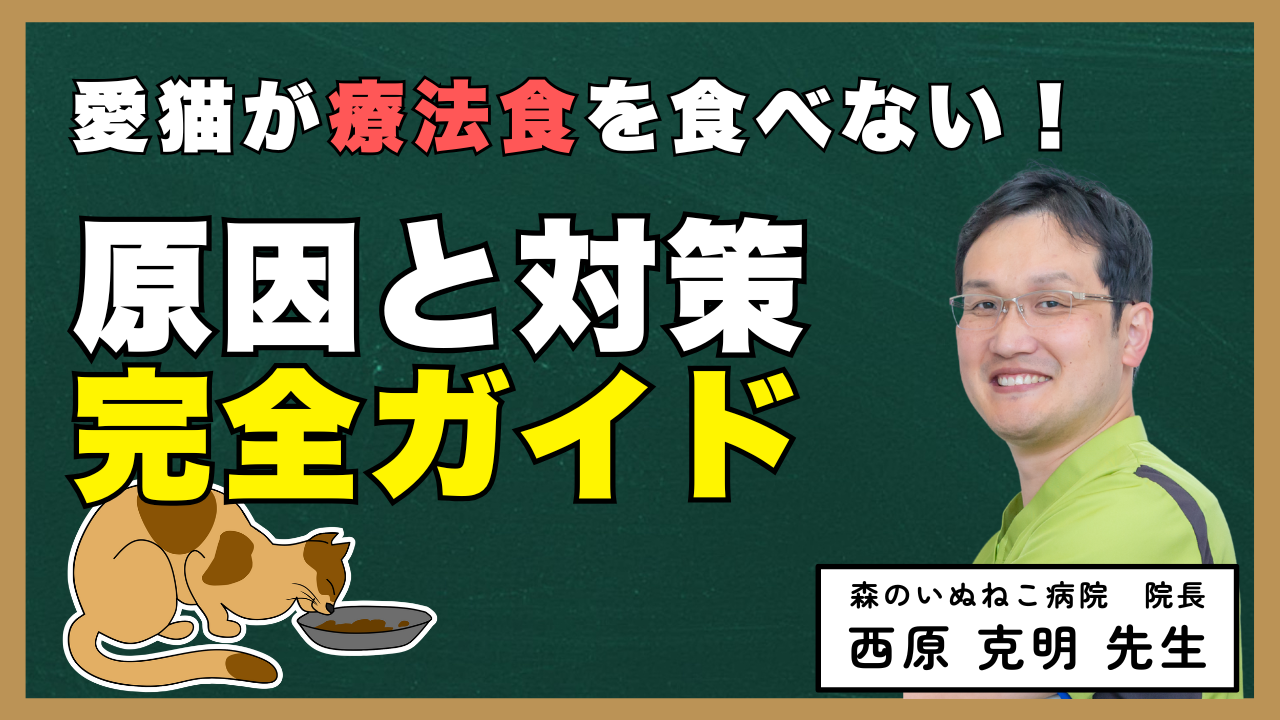なぜ猫は腎臓病になりやすいのか?
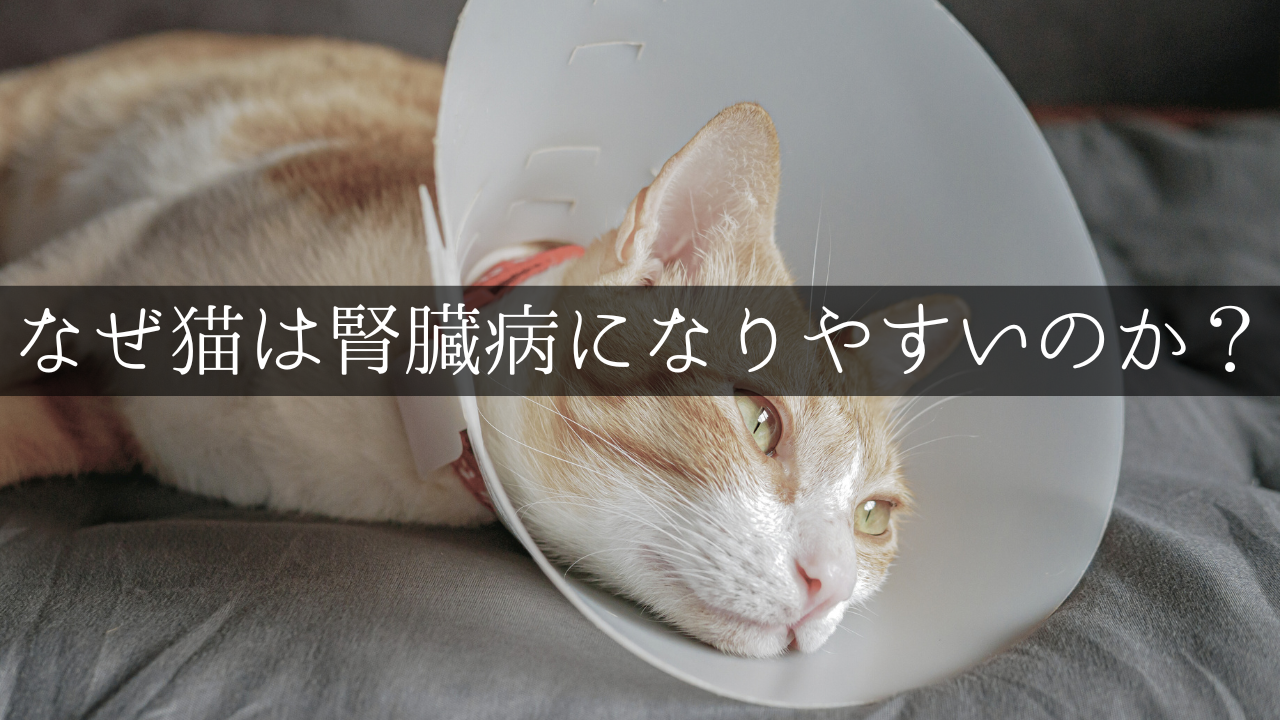
進化の過程で高機能になった腎臓
猫の祖先は砂漠地帯で生きてきた歴史があり、体内の水分を効率的に再吸収し、濃縮された尿を生成する能力を獲得しました。
この「高機能」な腎臓は、限られた水資源の中で生き抜くためには不可欠でした。
しかし、現代の猫の寿命が平均15年を超えるまでに延びたことで、生涯にわたって腎臓に大きな負担がかかり続けることになり、結果として、長期間にわたる酷使により腎臓の機能低下が顕在化しやすくなっています。
少ない「ネフロン」の数
猫の腎臓は、血液をろ過する機能単位である「ネフロン」の数が、人間(約200万個)や犬(約40万個)と比較して少ない(片方の腎臓につき約20万個)という特徴があります。
ネフロンは一度ダメージを受けると再生しないため、その数が少ない猫は、一度腎臓に問題が生じると機能低下が顕著になりやすい傾向があります。
これらの生物学的特性を考慮すると、猫の腎臓病は単なる加齢によるものだけでなく、その進化的な適応に起因する「宿命」とも言えます。
急性腎臓病と慢性腎臓病、何が違う?

猫の腎臓病は、その発症の仕方や進行度合いによって大きく二つのタイプに分けられます。
急性腎臓病(急性腎不全)
急性腎臓病は、数時間から数日で腎機能が急激に低下する病気です。
この病気は、脱水、心臓病による腎臓への血流減少、感染症、中毒(ユリ科植物の誤食など)、尿管結石による尿路閉塞などが原因で起こります。
急性腎臓病は進行が非常に早く、治療が遅れると命に関わることもありますが、適切な治療を受けることで腎機能が回復する可能性があります。
慢性腎臓病(慢性腎不全)
慢性腎臓病は、3ヶ月以上にわたり腎臓がダメージを受け続け、機能が徐々に低下していく病気です。
急性腎臓病とは異なり、一度失われた腎機能は回復しないと考えられており、残念ながら完治は期待できません。
そのため、慢性腎臓病の治療は、病気の進行をできる限り遅らせ、愛猫の生活の質を維持することに主眼が置かれます。
急性腎臓病と慢性腎臓病のこの根本的な違いは、単に病気の進行速度だけでなく、治療の「目的」と「予後」に決定的な差をもたらします。
猫の腎臓病、見逃せない症状と原因
急性腎臓病の具体的な症状と原因

主な症状は、突然ぐったりする、嘔吐、意識の低下、呼吸が荒い、排尿がほとんどないまたは全く出ないといった緊急性の高い状態が挙げられます。
その他、下痢、脱水症状、痙攣、体温低下、腹痛なども見られます。
原因は多岐にわたりますが、脱水や心臓病などによる腎臓への血流減少、細菌やウイルス感染、薬物や特定の植物(ユリ科植物)による中毒、尿管結石などによる尿路閉塞が主な要因として挙げられます。
特に、ユリ科の植物は、たとえ花瓶の水であっても猫にとって非常に危険であり、誤食は急性腎臓病を引き起こす重大な原因となります。
慢性腎臓病の具体的な症状と原因

主な症状は、初期の多飲多尿から始まり、進行すると薄い尿、便秘、体重減少、元気のなさ、嘔吐・下痢、口臭、被毛のツヤの喪失、貧血などが現れます。
しかし、この病気の最も厄介な点は、初期段階では症状がほとんど見られないことです。
猫は体調の悪さを隠すのが得意な動物であり、飼い主様が症状に気づいた時には、慢性腎臓病はすでにかなり進行している(腎機能の66%〜75%が失われている)可能性が高いとされています。
この「隠す習性」と「症状の遅発性」は、飼い主様による日々の注意深い観察(飲水量、尿量、食欲、体重)と、症状が出ていなくても定期的な健康診断が重要です。
症状が出てからでは、治療の選択肢が狭まり、手遅れになるリスクが高まります。
原因については、特定が難しいことが多いですが、加齢が最も主要なリスク要因であると考えられています。
その他、腎炎(細菌・ウイルス感染、免疫疾患)、外傷、薬物中毒、心筋症による腎血流低下、尿管結石や腎臓結石、歯周病、甲状腺機能亢進症などがリスクを高めることが知られています。
猫の腎臓病で制限すべき栄養素

慢性腎臓病の治療は、一度壊れてしまった腎臓の組織を回復させるものではなく、残された腎機能を保護し、病気の進行を緩やかにすること、そして体内に老廃物や毒素が溜まるのを防ぎ、症状を管理することが主体となります。
腎臓への負担を軽減するために、リン、タンパク質、ナトリウムを制限し、オメガ3脂肪酸や食物繊維などを強化した腎臓病用の特別療法食が治療の柱となります。
▶ リン
腎機能が低下すると、体内のリンを尿中に排泄しにくくなり、血液中のリン濃度が上昇します(高リン血症)。
高リン血症は、食欲不振、吐き気、血管や腎臓の石灰化、骨の弱化などを引き起こし、腎臓病の進行を加速させることが分かっています。
そのため、食事からのリン摂取を厳しく制限することが治療の重要です。
ただし、同じリンでも、有機リンと無機リンでは体への吸収の度合いが異なります。
例えば、お肉に含まれるリンは有機リンであり、お肉は体に必要なタンパク質の重要な供給源です。
そのため、リンの制限が必要な場合でも、お肉などから適量のタンパク質を摂ることは望ましいとされています。
リンの摂取を管理する際は、リンの種類による吸収の違いを理解し、他の必要な栄養素もバランス良く摂れるように食事を工夫することが、より良い食事管理につながります。
▶ タンパク質
タンパク質は猫にとって重要な栄養素であり、エネルギー源としても不可欠ですが、過剰に摂取すると、その分解時に窒素老廃物などの毒素が生成され、尿毒症の発症につながる危険性があります。
そのため、腎臓への負担を軽減するためにタンパク質の摂取量を制限する必要があります。
しかし、極端な制限は筋肉量の減少や栄養不足を招き、かえって猫の健康を損なう可能性があります。
したがって、単に制限するだけでなく、必要最低限の「高品質なタンパク質」を適切な量(療法食中のタンパク質割合が約26%程度)与えることが推奨されます。
鶏のささみや白身魚などが比較的適しているとされています。
▶ ナトリウム(塩分)
腎機能が低下すると、体内のナトリウム(塩分)を適切に排泄できなくなり、血液中に蓄積しやすくなります。
これにより体内の水分量が増加し、高血圧を引き起こします。
高血圧は腎臓病の進行を加速させる要因となるため、ナトリウムの制限も不可欠です。
ナトリウムは食品中では塩化ナトリウム(塩)の形で存在するため、塩分の高い食品は避けるべきです。
ソーセージ、ハム、チーズ、鰹節、しらす干しなど、人間用に調理された塩分の多い食品は、猫にとって過剰な塩分が含まれているため、腎臓病の猫には絶対に与えてはいけません。
猫の腎臓病で積極的に摂りたい栄養素

腎臓病の猫の食事療法では、制限すべき栄養素がある一方で、積極的に摂取したい栄養素もあります。
▶ オメガ3脂肪酸
腎臓病の進行を抑制し、抗酸化作用により腎機能を保護する効果が期待されます。
また、食欲が低下しがちな腎臓病の猫にとって、脂肪はエネルギー密度を高め、嗜好性を向上させるという点でも価値のある栄養素です。
マグロ、イワシ、サーモンなどの魚類、アーモンド、胡桃などのナッツ類、亜麻仁油、エゴマ油に多く含まれます。
ただし、適切な量を他の栄養素とのバランスを考慮して与えるのは非常に困難なため、サプリメントや、オメガ3脂肪酸が強化された療法食が推奨されます。
猫の療法食について詳しく知りたい方は以下のブログをご覧ください。
▶ 食物繊維
猫は肉食動物であるため、一般的に植物性の食物繊維はあまり必要としません。
しかし、腎臓病の猫において食物繊維を積極的に摂取することは、腸内細菌を増やし、血液中の有害物質(窒素老廃物など)を減少させることで、腎臓への負担を軽減する働きが期待されます。
レタス、キャベツ、水菜などの野菜や、舞茸、エリンギなどのきのこ類に豊富です。
ただし、猫は消化しにくいため、少量で細かく刻んで与えるなどの工夫が必要です。
▶ カリウム
慢性腎臓病の猫は、食欲不振による食事量減少や、多尿による水分喪失によって、低カリウム血症になりやすい傾向があります。
低カリウム血症は、筋力低下、食欲不振、活動性の低下、便秘などを引き起こすことがあります。
人間では低カリウム血症自体が腎機能を悪化させると言われているため、猫でも適切なカリウム摂取は腎機能の維持に望ましいとされています。
ただし、カリウムの過剰摂取は危険なので、必ず動物病院で検査を受けながら調節するようにしましょう。
カリウムは、バナナ、ほうれん草、さつまいも、豆類、魚類、肉類などに多く含まれます。
まとめ
猫の腎臓病は、多くの猫が罹患する病気であり、特に高齢猫に多く見られます。
猫は体調の悪さを隠すのが得意なため、症状が顕在化した時には病気がかなり進行していることが少なくありません。そのため、飼い主様による日々の注意深い観察と、定期的な健康診断、日々の食事に気を付けることが愛猫の命を救い、生活の質を維持するための鍵となります。
愛猫との健やかな日々を長く続けるために、今日からできることを実践していくことが大切です。
- 本記事の医師監修に関して学術部分のみの監修となり、医師が商品を選定・推奨している訳ではありません。