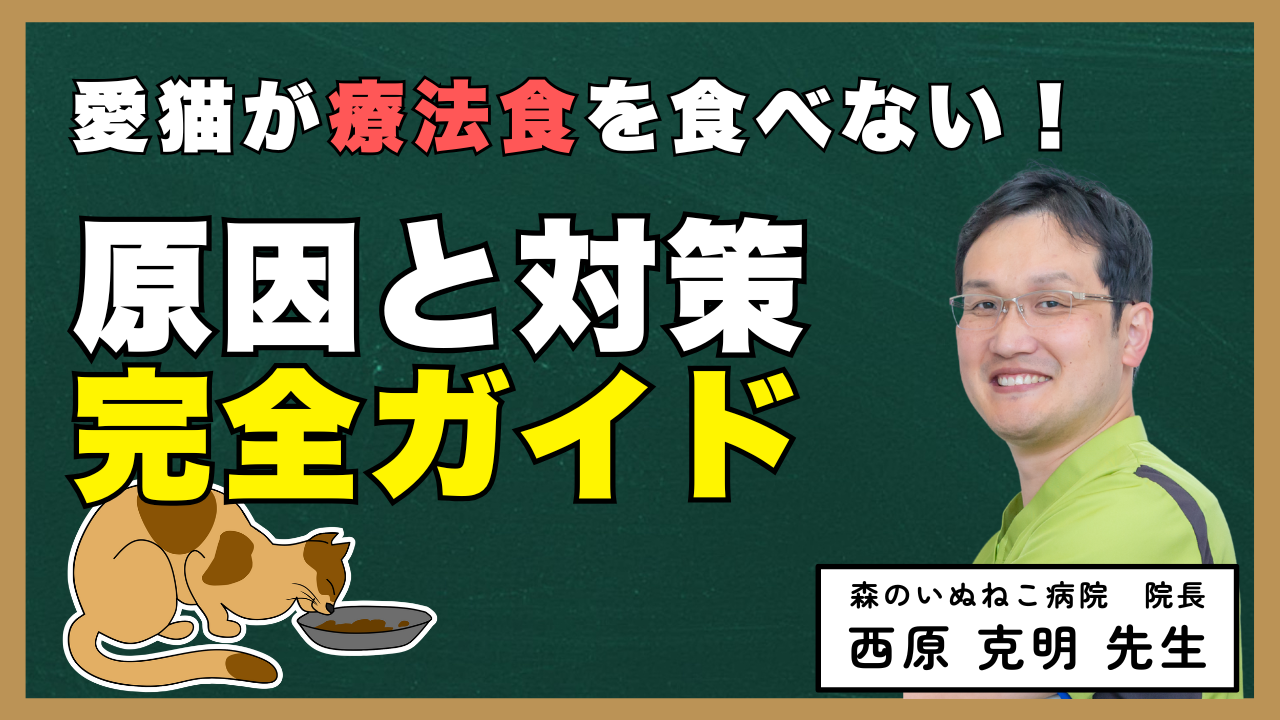なぜ愛猫は療法食を食べないのか?考えられる8つの原因
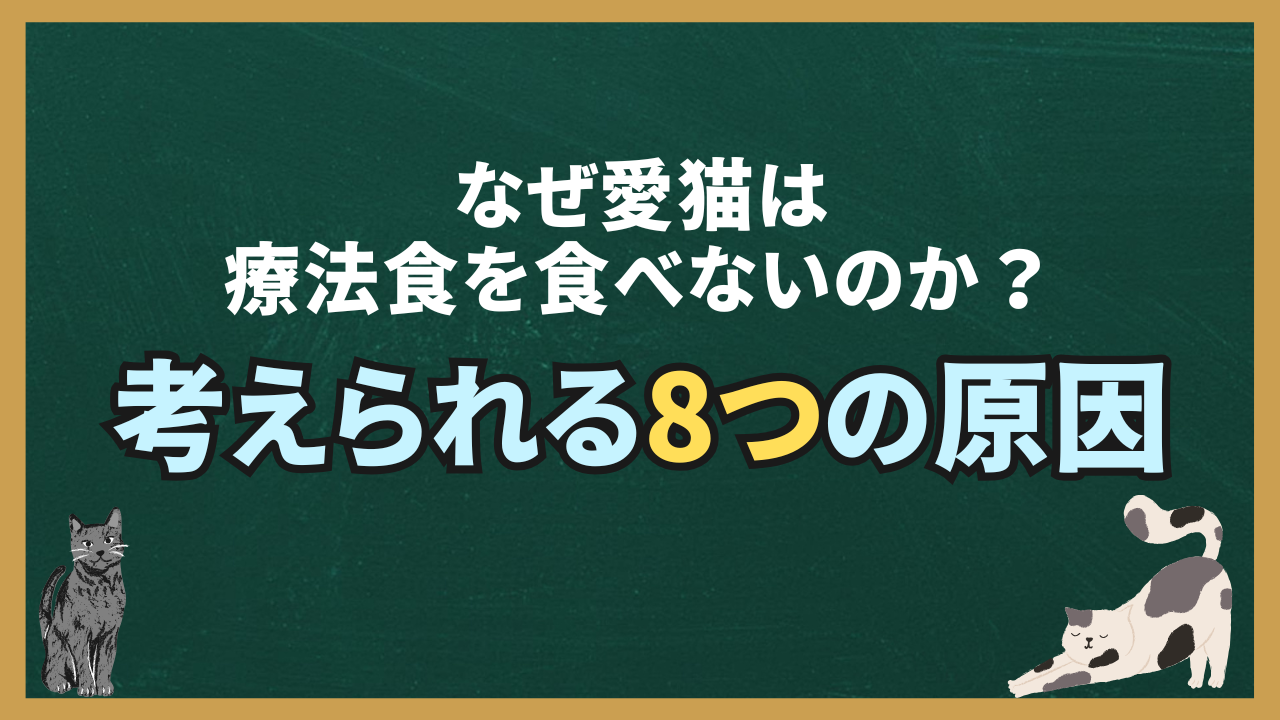
愛猫が療法食に口をつけないのには、様々な理由が考えられます。
単なる好き嫌いだけでなく、体調の変化や環境ストレスが隠れている場合もあります。
ここでは、主な原因を8つご紹介します。
1. 療法食への警戒心や飽き
猫は警戒心が非常に強い動物であり、新しいフードに対して抵抗を示すことがよくあります。
療法食は、これまでの一般的なフードとは味や香り、食感が大きく異なることが多く、猫が「これはいつものご飯ではない」と認識し、口をつけないケースが頻繁に見られます。
また、同じ療法食を長期間与え続けることで、猫がその味や香りに飽きてしまい、食いつきが悪くなることもあります。
療法食は、特定の栄養素(特にタンパク質)が制限されていることが多いため、一般的なフードに比べて嗜好性(しこうせい)が低く、飽きやすい傾向があるとも指摘されています。
2. 療法食の味や食感が合わない
猫は人間と比較して6倍以上もの嗅覚(きゅうかく)受容体を持っており、食べ物の匂いによって食べるか否かを判断すると言われています。
そのため、療法食の匂いが猫の好みに合わなかったり、ドライフードの粒の硬さや大きさ、ウェットフードの食感が気に入らなかったりすることも、食欲不振の大きな原因となります。
3. おやつや一般食の与えすぎ

療法食以外のおやつや一般食を与えすぎると、猫が療法食でお腹を満たさなくなり、結果的に療法食を食べなくなることがあります。
特に療法食は、特定の疾患の治療効果を最大限に引き出すために、栄養バランスが厳密に調整されています。
おやつなどによってそのバランスが崩れると、治療効果が損なわれるだけでなく、病状が悪化するリスクもあります。
4. 偏食
猫には「新しいもの好き」という習性があり、いつものフードに飽きて突然違うものを食べたがるようになることがあります。
これは病気やストレスではなく、猫本来の好奇心からくる行動です。飼い主様にとってはフードの買い置きが無駄になるなど困ることもありますが、猫の習性として理解しておくことが大切です。
5. 食事環境への不満やストレス

猫は非常に繊細な動物であり、食事環境のわずかな変化や不満が食欲不振につながることがあります。
食器、食事の場所を変更することで食べてくれるケースもあります。
6. 体調不良や病気が隠れている
食欲不振の原因として最も注意すべきは、病気が隠れているケースです。
療法食を必要とする猫は、すでに何らかの疾患(しっかん)を抱えていることが多いため、その病気の進行や、新たな病気の発症が食欲不振につながる可能性があります。
特に、高齢猫の発症率が高い腎臓病は、腎臓機能は一度損傷すると回復しないため、早期発見が極めて重要です。
猫の腎臓病について詳しく知りたい方は以下のブログをご覧ください。
【獣医師監修】猫の腎臓病は治らない?症状の原因や自宅でのケアまで徹底解説
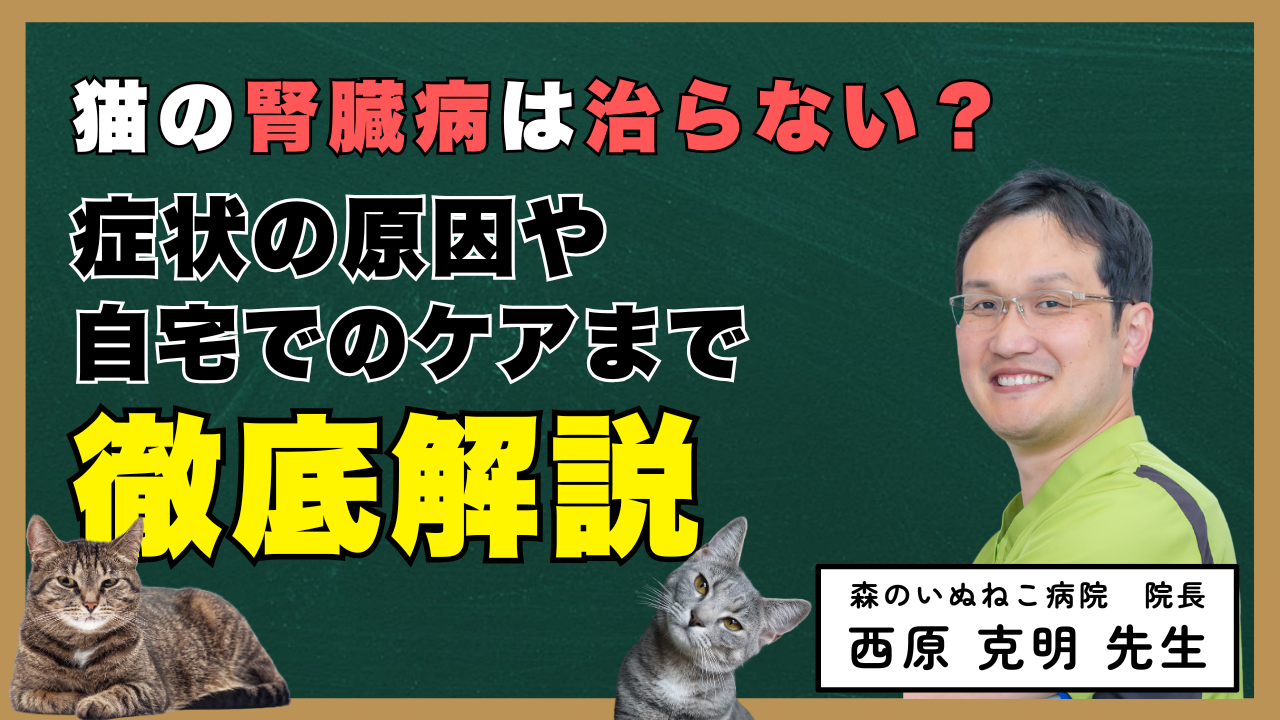
7. 加齢による食欲の変化
猫も人間と同様に高齢になると、活動量が減少し、それに伴って食事量も減少することがあります。
また、嗅覚(きゅうかく)や味覚などの感覚が衰え(おとろえ)、フードの匂いを十分に感じられなくなることも食欲不振の原因となります。
さらに、噛む力が弱くなる老猫の場合、ドライフードが固くて食べ疲れてしまう可能性も考えられます。
8. 発情期による食欲減退
去勢(きょせい)・避妊(ひにん)手術をしていない猫の場合、春や秋、冬などの発情期(はつじょうき)に食欲が落ちることがあります。
これは、ホルモンバランスの変化や、食べ物よりも異性への関心が強くなるためと考えられます。
一時的な食欲不振であれば問題ありませんが、長期にわたる場合は獣医師に相談しましょう。
愛猫が療法食を食べるための8つの対策
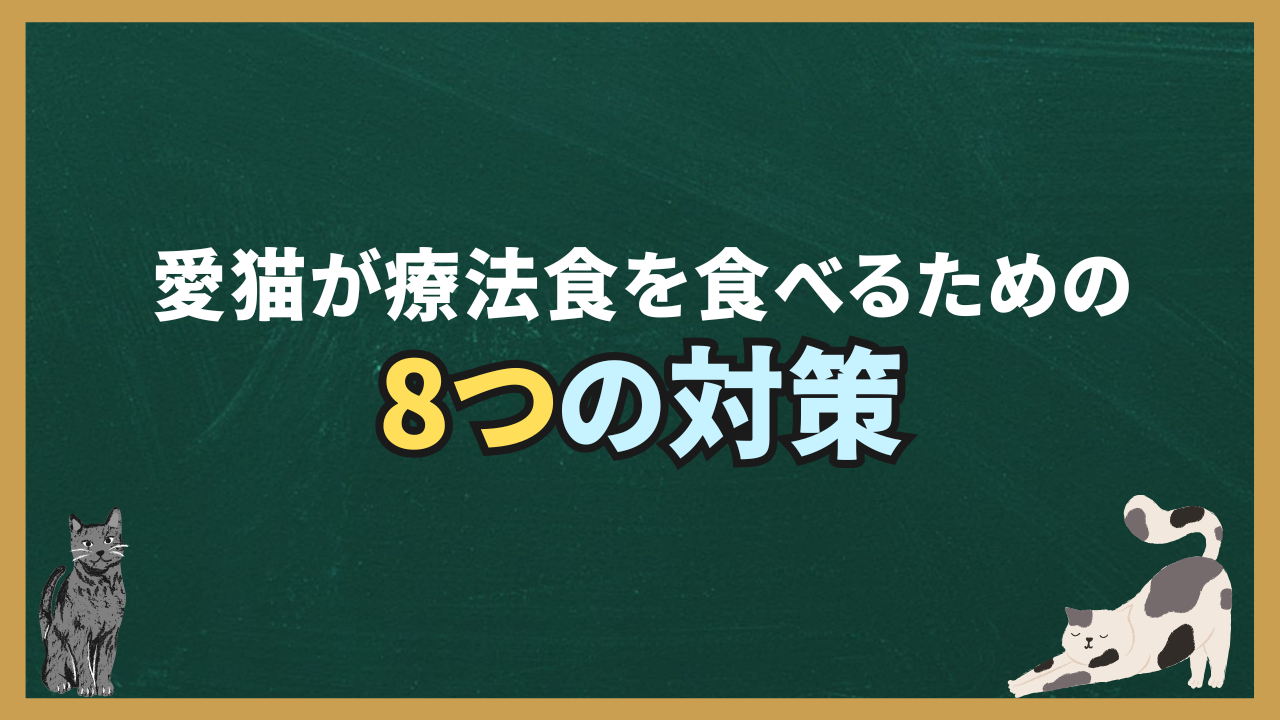
愛猫が療法食を食べてくれない時、飼い主様ができることはたくさんあります。
焦らず、愛猫のペースに合わせて様々な方法を試してみましょう。
1. 獣医師に相談する
療法食は、ネットショッピングでも気軽に購入できるようになりましたが、本来は特定の疾患(しっかん)の治療や管理のために獣医師の指導のもとで与えられる「特別処方食」です。
愛猫が療法食を食べない状況が続く場合は、必ず獣医師に相談し、その原因の特定と適切な対策についてアドバイスを求めましょう。
獣医師は、愛猫の病状や体質、個性、そして飼い主様の状況に合わせた最適な方法を提案してくれます。
例えば、食欲増進剤(しょくよくぞうしんざい)の処方や、異なる種類の療法食の提案など、多岐にわたる選択肢を提案してくれます。
2. 段階的に療法食へ切り替える

猫の強い警戒心を解き、新しい療法食に慣れさせるためには、急にフードを切り替えるのではなく、段階的に移行することが非常に重要です。
理想的には、1週間から10日間程度かけて、少量(例えば1割程度)の療法食を通常のフードに混ぜることから始め、猫の様子を見ながら徐々に療法食の割合を増やしていく方法が推奨されます。
3. 香りを立たせて食欲を刺激する
猫は嗅覚(きゅうかく)が非常に優れており、食べ物の匂いによって食欲が大きく左右されます。そのため、フードの香りを強くすることで、食欲を刺激し、療法食への関心を高めることができます。
電子レンジや湯煎(ゆせん)を使って人肌程度に温めたりすることで、香りが立ち、食べてくれたりします。
また、フードに匂いをつける方法も有効です。
例えば、鰹節や煮干しを少量、お茶パックやネットに入れて療法食の袋の中に一緒に入れておくと、香りだけがフードに移り、猫が興味を示しやすくなります。
4. 味や食感の異なる療法食を試す
同じ病気を対象とした療法食であっても、メーカーによって味や匂い、食感が大きく異なります。
愛猫が特定の療法食を頑なに拒否する場合、別のメーカーの療法食を試してみることで、問題が解決する可能性があります。
ただし、先に記述した通り療法食は「特別処方食」ですので、必ず獣医師に相談するようにしましょう。
5. フードの形状や与え方を工夫する

猫の好みは、フードの粒の大きさや硬さ、与え方によっても変化します。
例えば、噛む力が弱い老猫や体力が落ちた猫には、ドライフードをぬるま湯やスープ、ペット用ミルクなどでふやかして与えることで、食べやすくなります。
最近では猫の健康に配慮したおやつもあるため、ドライフードにそのようなおやつをトッピングするのも有効です。
与え方では、食器から直接食べない場合でも、飼い主様の手のひらにフードを乗せて与えると、食べてくれることがあります。
手軽にできるので色々試してみましょう。
6. 食事環境を整える
猫が安心して食事できる環境を整えることは、食欲を促す上で非常に重要です。
食器は、ヒゲの当たらない、平べったい陶器製のものを選びましょう。
食後は毎回きれいに洗い、洗剤の残り香がないようしっかりとすすぎましょう。
環境では、静かで落ち着ける場所で食事させましょう。
猫は暗く狭い場所に安心感を覚えるため、ダンボール箱などを利用して食事場所を用意してあげるのも有効です。
7. 適度な運動で空腹感を促す

食事の前に愛猫と遊んで運動させることで、お腹を空かせ、食欲を促す効果が期待できます。
キャットタワーなどで体を動かすことは、運動不足やストレスの解消にもつながり、日々の健康維持にも貢献します。
ただし、病気で体力が低下している猫の場合は、無理な運動は避け、獣医師と相談して適切な運動量を決めるようにしましょう。
8. 無理強いはしない
療法食をなんとしても食べさせようと無理強いすることは、猫にとって大きなストレスとなり、「フードを食べることは嫌なこと」という負の感情を植え付けてしまう可能性があります。
一度嫌悪感(けんおかん)を抱いてしまうと、その後も食事をしたがらなくなるなど、長期的な問題につながる恐れがあるため、食事の無理強いは厳禁です。
愛猫の体調や感情を尊重し、焦らず、様々な方法を試しながら、猫が自ら食べてくれるようなアプローチを続けることが大切です。
まとめ
愛猫が療法食を食べないという問題は、単なる食事の好みを超え、療法食への警戒心や味・食感の不適合といった心理的・感覚的な要因から、食事環境のストレス、さらには慢性腎臓病をはじめとする深刻な病気のサインまで多岐にわたります。
特に、慢性腎臓病のように症状が進行してから顕在化する疾患の場合、飼い主様による早期の兆候察知と迅速な獣医師への相談が、愛猫の予後を大きく左右する可能性があります。
愛猫の健康を守るためには、飼い主様が抱える不安を一人で抱え込まず、獣医師という専門家と協力し、愛猫の個性と状態に合わせた最適なケアを継続していくことが不可欠です。
愛猫と飼い主様が共に健康で幸せな日々を送るための一助となることを願っています。
- 本記事の医師監修に関して学術部分のみの監修となり、医師が商品を選定・推奨している訳ではありません。