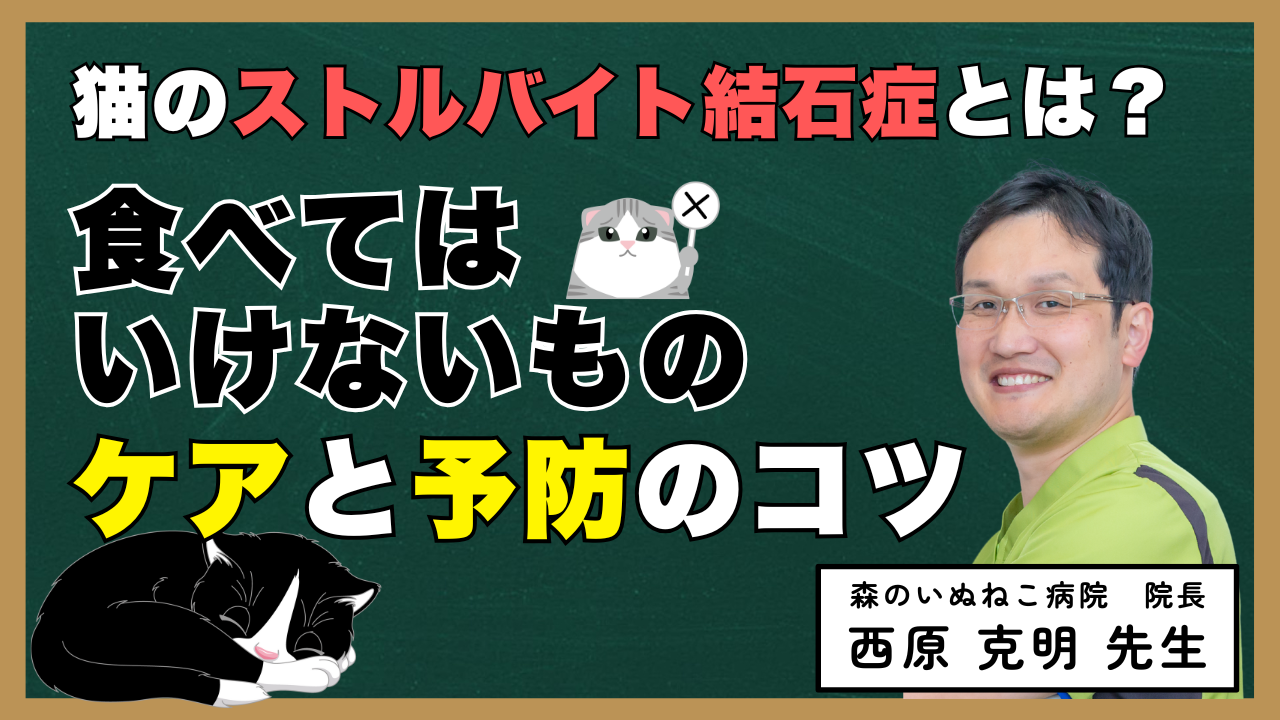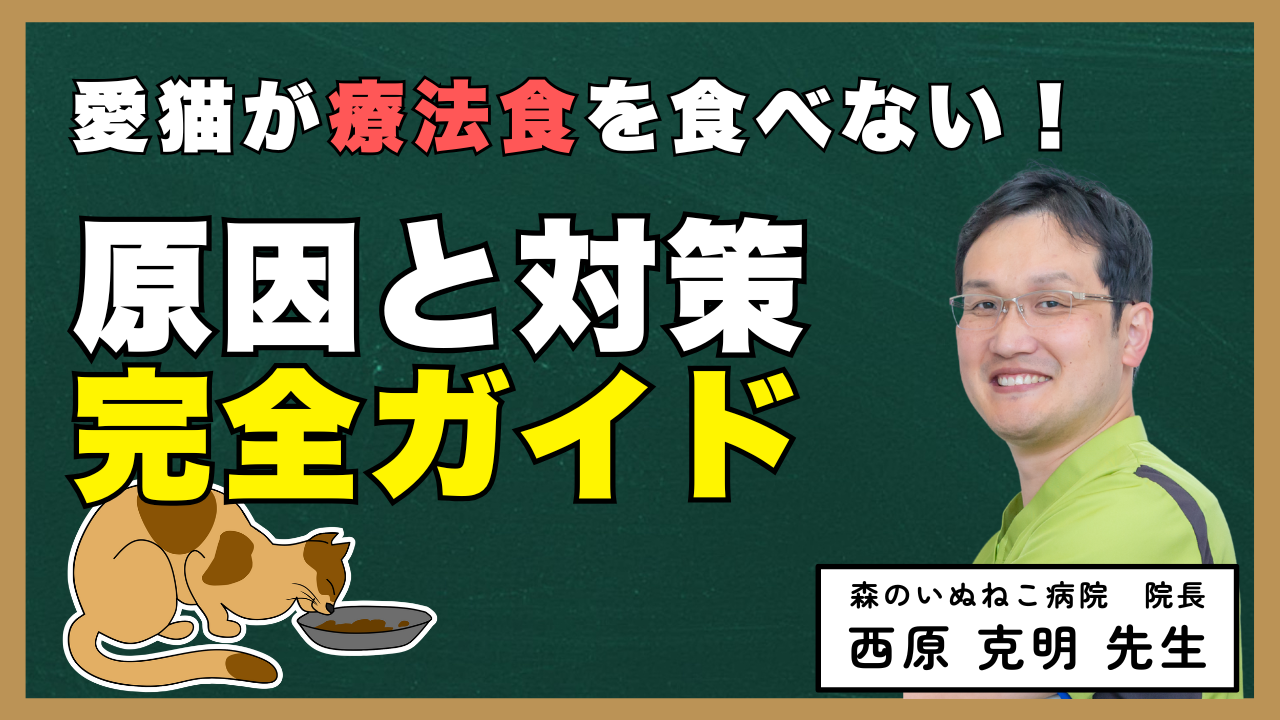ストルバイト結石とは?
猫の「尿路結石症(にょうろけっせきしょう)」は、腎臓から尿道までの尿の通り道(尿路)のどこかに結晶や結石が形成される病気の総称です。
この疾患は、排尿時の痛み、頻尿、尿の濁り、血尿などの症状を引き起こし、結石が尿路を完全に塞いでしまう「尿閉塞」に至ると、体内に毒素が蓄積し「尿毒症」を引き起こす可能性があり、命に関わる緊急事態となります。
尿路結石にはいくつかの種類が存在しますが、猫で特に多く見られるのは「ストルバイト結石」と「シュウ酸カルシウム結石」です。
ストルバイト結石
正式名称は「リン酸アンモニウムマグネシウム」といい、尿がアルカリ性(pH7以上)に傾くと形成されやすくなります。
特に7歳以下の猫に多く見られる傾向があり、このタイプの結石は、適切な食事療法によって溶解させることが可能です。
シュウ酸カルシウム結石
尿が酸性に傾くとできやすくなる結石です。
一度形成されると食事療法では溶解しないため、外科手術が必要となる場合が多く、予防が非常に重要となります。
なぜストルバイト結石は食事管理が重要なのか

猫の尿路結石症、特にストルバイト結石の形成には、日々の食事内容が大きく影響を及ぼします。
食事によって尿のpHが変動し、結石の構成成分となる特定のミネラル(マグネシウム、リン、アンモニウムなど)が尿中で過剰になると、結晶化が促進されやすくなるためです。
適切な食事管理は、すでに形成されたストルバイト結石を溶解させるだけでなく、再発を効果的に予防する上で最も重要な要素の一つです。
適切な栄養バランスの食事は、尿のpHを理想的な範囲にコントロールし、結石の構成成分となるミネラルのバランスを調整することで、泌尿器系に負担の少ない環境を維持する助けとなります。
ただ、猫は好き嫌いの多い動物です。
療法食を与えたくても受け付けてくれないことも少なくありません。
猫の療法食について詳しく知りたい方は以下のブログをご覧ください。
猫のストルバイト結石を悪化させる「食べてはいけないもの」リスト

ストルバイト結石を患う猫には、尿をアルカリ性に傾けたり、結石の主要成分となるミネラル(マグネシウム、リン、アンモニウム)を過剰に含んだり、消化器系に負担をかける可能性のある食材は避けるべきです。
高マグネシウム・高リン含有食材

これらのミネラルはストルバイト結石の主要な構成要素であるため、摂取量を制限することが重要です。
▶ 煮干し、かつおぶし
猫が好むおやつとして広く知られていますが、リンやマグネシウムなどのミネラルが非常に豊富に含まれています。
特に煮干しは栄養が凝縮されており、保存性を高めるために塩分が添加されている場合もあるため、結石形成のリスクを著しく高めます。
▶ 海藻類(のり、わかめなど)
マグネシウム含有量が非常に高く、尿のpHをアルカリ性に傾ける可能性があるため、少量であっても摂取は避けるべきです。
▶ アーモンド、ピーナッツ
マグネシウムを多量に含むため、注意が必要です。
▶ 青魚(サバ、イワシなど)
リンやマグネシウムが豊富に含まれています。白身魚と比較しても含有量が高いため、尿石症の猫には与えない方が良いでしょう。
猫にとって理想的なミネラルバランスは「カルシウム:リン:マグネシウム=1.2:1:0.08」とされています。
このバランスが崩れると、尿中のミネラルが結晶化しやすくなります。
特にマグネシウムが過剰になると尿がアルカリ性に傾きやすくなり、ストルバイト結石の形成が促進されることが知られています。
単に特定のミネラルが多いから避けるのではなく、体内のミネラルバランス全体への影響を考慮することが重要です。
過剰なタンパク質・消化しにくい食材
消化に負担をかける食材や、タンパク質の過剰摂取も尿路環境に影響を及ぼすことがあります。
▶ ささみ(与えすぎの場合)
過剰な摂取は、腎不全や肝不全といった既存の病態を悪化させるリスクが指摘されています。
▶ ジャーキーなどの肉類おやつ
高タンパク質であり、リンやマグネシウムを多く含む場合があります。
▶ 加工肉(ハム、ベーコン、ソーセージなど)
リンやマグネシウムが豊富です。
脂肪分やカロリーが高く、肥満の原因にもなり、肥満は尿石症の要因の一つとして認識されています。
植物性タンパク質・穀類・特定の野菜

猫は本来、完全肉食動物であるため、植物性食材の消化には適していません。
▶ 大豆製品(大豆、おから、納豆、枝豆、レンズ豆など)
マグネシウムやリンを豊富に含み、猫の尿pHをアルカリ性に傾ける大きな要因となります。
大豆に含まれる成分は猫の腸壁を傷つけたり、甲状腺を刺激したりする可能性も指摘されており、手作り食においても避けるべき食材です。
▶ 小麦、トウモロコシなどの穀類
猫は穀類を食べる動物ではないため、消化器に負担をかけ、高糖質であることから肥満の原因にもなります。
小麦に含まれるグルテンが腸壁を傷つける可能性も指摘されています。
▶ ナス科の植物(トマト、ナス、ピーマン、ジャガイモ)
猫には厳禁とされています。
▶ サツマイモ、野菜の与えすぎ
野菜の与えすぎは猫の尿をアルカリ性に傾ける大きな要因となります。
サツマイモも猫の健康維持には必ずしも必要ではなく、避けるべき食材とされています。
その他、注意すべき食品
▶ ミネラルウォーター
ミネラル分の過剰摂取につながる可能性があるため、与える際には注意が必要です。
▶ 添加物や調味料が多いフード
塩分や糖分が多い製品は尿を濃縮させ、結石形成を促進する要因となります。
消化しづらい添加物も尿のアルカリ化を招く可能性があるため、成分表示をよく確認し、添加物の少ないフードを選ぶことが好ましいです。
ストルバイト結石の予防とケア

食事管理だけでなく、日々の生活環境も尿路結石の予防とケアに大きく影響します。
十分な水分摂取の工夫
猫は元来、砂漠で暮らしていた祖先を持つため、積極的に水を飲む動物ではありません。
しかし、尿量を増やし、尿の濃度を薄めることは、尿中の結晶が結石に成長するのを防ぎ、尿路から排泄されやすくするために非常に重要です。
これにより、最も危険な尿閉塞を予防する目的があります。
「猫に水を飲ませる」ことは、ストルバイト結晶の形成そのものを直接的に防ぐものではなく、尿量を増やして尿を薄めることで、結晶が大きくなるのを防ぎ、尿路から排出されやすくし、尿閉塞のリスクを低減するための「対症療法」としての側面が強いことを理解しておくべきです。
具体的な水分摂取の工夫には以下が挙げられます。
▶ ウェットフードの活用
ドライフードに比べて水分量が80%前後と非常に多いため、食事から効率的に水分を摂取できます。
また、香りが強く食いつきが良い傾向があるため、猫が喜んで水分を摂る助けとなります 。
▶ フリーズドライフードをふやかす
フリーズドライのキャットフードを水分でふやかすことで、水分摂取量を増やすことができます。
▶ 飲み水の改善
- 猫が飲みたくなるような新鮮で美味しい水(軟水など)に変える。
- 流れる水を好む猫のために、循環式給水器を設置する。
- 複数の場所に水飲み場を設置し、器の種類を変える(陶器、ガラス、ステンレスなど)ことで、猫が好む飲み方を見つける。多頭飼育の場合は、猫の数よりも多い数の水飲み場を用意することが推奨されます。
▶ トイレの回数を増やす
膀胱内に尿が溜まっている時間が長いと、尿中のミネラル濃度が高まり結石ができやすくなります。
猫が頻繁に排泄できる環境を整えることも重要です。
適切な食事回数と与え方(置き餌を避ける)

猫の健康にとって置き餌はメリットがないため、一気に与えるのではなく、分けて少量ずつ与えることが推奨されます。
猫のストレスにならないよう、徐々に1日4~5食から1日2食に近づけていくことを目指しましょう。
市販のプレミアムフードの中にも、猫の尿pHを高くする原材料が多く使われている場合があるため、フードを選ぶ際は、表面の謳い文句だけでなく、必ずラベル裏の「原材料表示」や「成分表示」をきちんと確認することが重要です。
ストレス軽減と快適な環境作り

膀胱炎は尿石症の原因となることもあるため、ストレス軽減は結石予防とケアにおいて重要な要素です。
具体的な対策としては、以下が挙げられます。
▶ 運動不足の解消とコミュニケーション
キャットタワーなどを活用して運動不足を解消し、遊びを通して飼い主様とのコミュニケーションを増やすことで、ストレスを軽減できます。
▶ 静かで落ち着ける環境
猫がリラックスして過ごせる静かで落ち着いた環境を提供することが大切です。
▶ トイレ環境の最適化
トイレの清潔さを保つことはもちろん、猫が快適に排泄できるような形状、サイズ、場所、砂の種類を選ぶことも重要です。
猫はトイレ環境に非常に敏感な動物です。
▶ 適切な体重管理
肥満は尿石症の要因の一つであるため、適切な体重を維持することも重要です。
定期的な健康チェックと獣医師との連携
尿路結石症は再発しやすい病気であり、早期発見と早期治療が重要です。
定期的な尿検査は、再発を早期に発見し、適切な対策を講じる上で非常に有効です。
まとめ
猫のストルバイト結石症は、食事内容と尿のpHバランスが深く関わる疾患です。この病気を予防し、適切にケアするためには、飼い主様のきめ細やかな配慮が求められます。
日頃から愛猫の排尿の様子を注意深く観察し、異変に気づいたらすぐに動物病院を受診することで、早期発見・早期治療につながり、愛猫の命と健康を守りましょう。
- 本記事の医師監修に関して学術部分のみの監修となり、医師が商品を選定・推奨している訳ではありません。